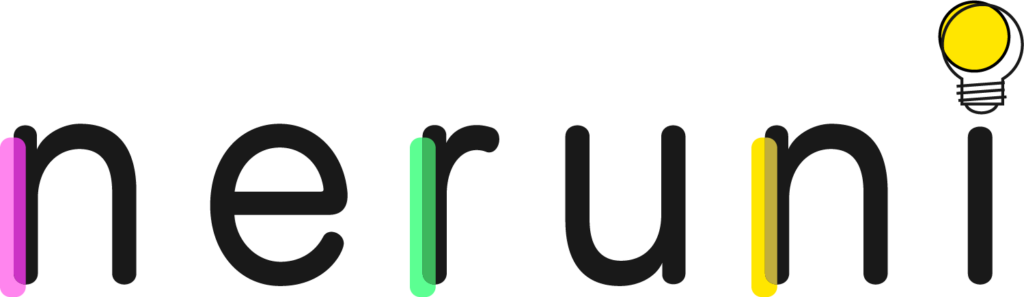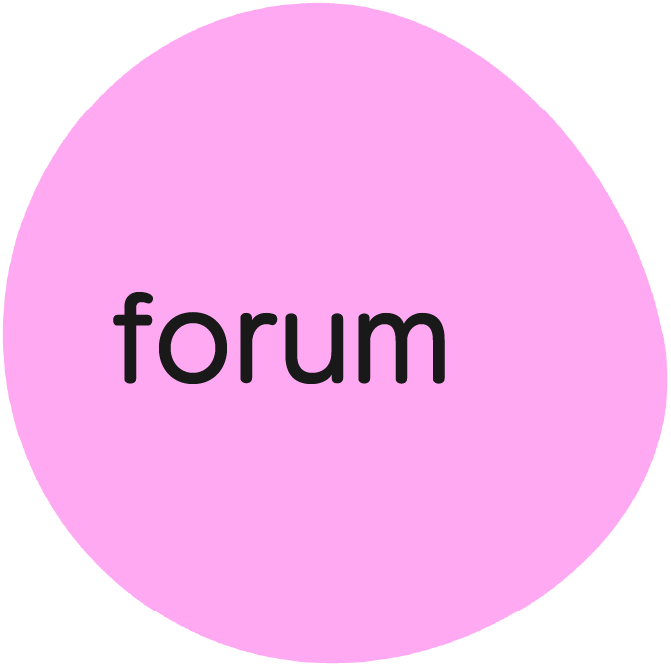災害が頻発する日本では、安心して暮らせる社会を築くために、防災や減災の取り組みが欠かせません。しかし、「防災」と「減災」という言葉が具体的にどのような意味を持つのか、また実際にどんな対策が進められているのか、まだ十分に知られていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、防災・減災の基本的な考え方をはじめ、各地の地方自治体が行う具体的な取り組みや浜松市の事例をご紹介します。未来の災害に備えるヒントとして、ぜひご覧ください。
災害対策における「防災」と「減災」
災害大国と言われる日本では、災害への備えが非常に重要です。その中でも、「防災」と「減災」という2つの概念が広く使われています。どちらも災害対策の一環ですが、それぞれ異なる視点とアプローチがあります。ここでは、防災と減災の違いや特徴について詳しく見ていきましょう。
防災
防災とは、災害を未然に防いだり、被害を最小限に抑えるための事前対策を指します。地震や台風、洪水などの自然災害に対し、被害を「ゼロ」に近づけることを目指してさまざまな準備を行うのが特徴です。
例えば、耐震性の高い建物の設計、堤防や排水設備といったインフラの整備が挙げられます。また、避難計画を策定し、災害時の迅速な対応ができるよう訓練を重ねることも防災の一環です。
防災は、可能な限りリスクを排除するための取り組みですが、自然災害を完全に予測することが難しいため、想定外の被害が生じる可能性もあります。そのため、防災は災害対策の土台として機能すると言えるでしょう。
減災
減災は、災害が起こることを前提に、その被害を最小限に抑えることを目指す考え方です。減災の取り組みが広まったきっかけは、1995年の阪神淡路大震災であると言われています。大きな災害を経て、防災だけではすべての被害を防ぎきれないという考え方が浸透していきました。
減災の取り組みでは、「公助」「自助」「共助」の連携が重視され、個人や地域、行政が協力し合うことで、被害を軽減する具体的な対策が進められます。例えば、ハザードマップを活用して避難ルートを事前に確認したり、避難訓練を実施するなどがその一例です。
「防災」と「減災」はそれぞれ異なる意味を持つものの、実際には減災の考え方が「防災」の一部として捉えられることも多くあります。また、それぞれの対策が実際の現場では重なり合い、互いを補完する形で活用されているのが一般的です。
減災のために重視すべきポイント

自然災害は避けられないものですが、その被害を最小限に抑えることは可能です。減災を実現するためには、日頃の備えと行動が重要となります。ここでは、特に注目すべき7つのポイントを詳しく解説します。
自助と共助の強化
減災において、特に重要なのが「自助」と「共助」です。「自助」とは、自分自身や家族の安全を守るために備えることであり、これが減災の基本となります。災害時に行政の支援(公助)が届くまでには時間がかかる場合があるため、まずは自身でできることを準備しておくことが大切です。
例えば、「自助」では、非常持ち出し袋を準備したり、家族全員で避難ルートを確認しておくことが有効です。また、「共助」の観点では、地域の防災訓練に参加し、近隣住民同士で連携を図ることが効果的でしょう。
さらに、次のような質問を日々考えることで備えを強化できます。
自分自身でできる減災対策は何か。
家族で協力して取り組める準備はあるか。
地域の人々と協力して進められる活動は何か。
これらの意識を持つことで、災害による被害を最小限に抑えることが可能となります
ハザードマップの活用
地域の危険性を把握し、災害時に迅速な行動を取るためには、ハザードマップが役に立ちます。ハザードマップとは、地震や洪水、土砂災害などの危険性・避難場所・避難経路が示されているマップです。自分の住んでいる地域で、どのようなリスクがあるのかを事前に理解することができます。
ハザードマップは、市役所や公民館で配布されているほか、自治体のホームページでも閲覧可能です。家族全員でマップを見ながら避難場所や安全なルートを確認し、実際に歩いてみるとさらに理解が深まります。緊急時に慌てることなく安全に行動するためにも、日頃から準備を進めておきましょう。
防災グッズと備蓄品の準備
災害時に慌てず対応するためには、防災グッズや備蓄品を日ごろからしっかり準備しておくことが大切です。準備は「外出時」と「自宅用」の2つの視点で考えましょう。
外出時に持ち歩くべきもの
身分証明書(運転免許証、保険証、診察券)
緊急時のための水や軽食(チョコレート、飴など)
携帯用ラジオ、モバイルバッテリー
笛やハンカチなどのSOS用アイテム
自宅で備えておくべきもの
最低3日分の水や食料(非常用食品)
懐中電灯、予備電池、手回しラジオ
常備薬や必要な衛生用品(マスク、消毒液)
履きやすい靴、手袋、レインコート
これらの準備は、いざという時に命を守る大きな助けとなります。また、定期的に内容を見直し、有効期限を確認しておくことも忘れないようにしましょう。
建物の耐震化
地震の被害を減らすためには、建物の耐震性を高めることが不可欠です。まず、自宅が昭和56年6月以降の新耐震基準で建てられているかどうかを確認しましょう。それ以前に建てられた家は耐震性が不足している可能性があるため、耐震診断を受けることをおすすめします。診断結果に応じて、耐震補強を行えば倒壊リスクを大幅に軽減できます。
また、新耐震基準に沿った建物であっても、壁の配置バランスが悪い場合や築年数による劣化が進んでいる場合には注意が必要です。特に1階部分に大きな窓や出入口が多い構造では、耐震性が十分でないケースもあります。自治体によっては耐震診断や補強工事に対する補助金制度を設けているため、活用するのも良いでしょう。
さらに、地震保険や共済保険に加入し、地震後の経済的負担を軽減する準備も重要です。耐震化への取り組みは、自分と家族の命を守るだけでなく、地域全体の安全向上にもつながります。
家具の固定と安全空間の確保
地震時の負傷原因として、家具の転倒や落下が大きな割合を占めると言われています。そのため、家具の固定は命を守るための基本的な対策です。背の高い家具や重い家電製品は、壁や床にしっかりと固定しましょう。また、ガラス飛散防止フィルムを窓や棚のガラス部分に貼ることで、破損時の危険を軽減できます。
さらに、自宅内には「安全空間」を確保することも重要です。家具の配置を工夫し、倒れにくい場所に置くことで、寝室や子供部屋、お年寄りが過ごす部屋などをより安全に保てます。特に、「家具の上に重い物を置かない」「低い家具を選ぶ」といった配慮が有効です。
家族間での防災計画の共有
災害時には家族が一緒にいるとは限らないため、事前に防災計画を共有しておくことが大切です。例えば、安否確認の連絡方法や非常時の集合場所、各自の学校や職場の避難先について話し合い、明確にしておきましょう。また、小さなお子さんがいる場合は、保育園や学校での災害時対応について確認し、引き取り手順を把握しておく必要があります。
さらに、離れて暮らす親戚や信頼できる知人にも、非常時の連絡先や対応について伝えておくと安心です。こうした計画を日頃から話し合うことで、家族全員が災害時に落ち着いて行動できるようになるでしょう。
地域とのつながりの強化
災害時に「共助」を実現するためには、日ごろから地域とのつながりを深めておくことが大切です。近隣の方々と日常的に挨拶や会話を交わしておくと、災害時にお互いを助け合える関係が築けます。また、子どもや高齢者、障害のある方など、特に支援が必要な人が近くにいる場合は、その情報を地域で共有しておくと、緊急時にスムーズに対応できるでしょう。
さらに、町内会や自治会で行われる防災訓練や炊き出しに参加することもおすすめです。地域の防災体制を知り、自身の役割を意識することにつながります。
参考:減災のてびき|内閣府
地方自治体における防災・減災の取り組み事例
地方自治体では、自然災害から命と暮らしを守るため、さまざまな防災・減災の取り組みが進められています。ここでは、地域特性を活かした取り組み事例を5つご紹介します。
地域別ハザードマップの作成
新潟県では豪雨や津波といった災害リスクを細かく分析し、地域に特化したマップを住民とともに作成する取り組みが行われました。住民参加型のワークショップが実施され、避難場所や津波の進行方向、高層ビルの位置など、住民にとって必要な情報が盛り込まれているのが特徴です。
また、地図の精度を高めるだけでなく、矢印などを用いて視覚的に分かりやすいデザインにする工夫もされています。完成したマップは家庭や学校に配布され、防災教育にも活用されています。
下水道整備
下水道の整備は、集中豪雨による浸水被害を防ぐための重要な対策の一つです。例えば、神戸市では、古い水路を拡大・更新し、雨水幹線や貯留施設の整備を進めています。雨水を一時的に溜めて、降雨が収まった後に排水する仕組みは、短時間で大量の雨が降る都市部で特に効果を発揮します。
さらに、地盤が低く雨水が自然に流れにくい地域には、ポンプ場を設置して雨水を強制的に海や川へ排水する対策が取られています。これにより、浸水被害のリスクが大幅に軽減され、安全な街づくりが推進されているのです。
参考:浸水から街を守る|神戸市
防災公園の整備
防災公園の整備は、災害時の避難拠点や救助活動の拠点として、大きな役割を果たしています。例えば、佐賀県武雄市では、防災公園の整備により、災害時に500人を収容可能な避難施設を確保しており、実際に令和6年台風第10号の際に避難所として機能しました。この公園には、防災機能を強化するため、空調設備の整った体育館や、救助車両の駐車スペースが拡充されています。
防災公園は、平常時には防災訓練や炊き出し、入浴支援の場としても活用されています。通常の公園としての役割はもちろん、災害用トイレやかまどベンチ、防災井戸ポンプなどの設備を備えられている点が特徴的です。
IoTとAIの活用
近年、地方自治体では、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の活用が進んでいます。例えば、IoTセンサーを活用した災害監視システムでは、地震や河川の水位、土砂崩れのリスクをリアルタイムで把握し、迅速な警報発信を可能にしています。また、気象データや地形情報をAIが分析することで、被害の予測精度が向上し、住民への適切な避難誘導を実現しています。
福岡県糸島市では、IoTと地理情報システムを活用し、災害情報の入力や共有を効率化する取り組みが導入されました。一方、香川県高松市では、水位センサーやカメラを用いて、河川や避難所の状況をリアルタイムでモニタリングし、災害時の迅速な対応に役立てています。このような技術活用は、防災・減災における新たな可能性を開いています。
VRを用いた防災訓練
VR(仮想現実)技術を活用した防災訓練は、災害時のリアルな状況を疑似体験することで、住民の防災意識を高める取り組みとして注目されています。例えば、仙台市では「せんだい災害VR」という防災学習サービスを展開し、地震や津波といった災害を仮想空間で体験できる機会を設けています。専用のスタッフが地域の学校や集会所を訪問し、住民が災害時の行動を具体的にイメージしやすい環境を作り出していることが特徴的です。
また、東日本大震災の教訓を活かし、災害時の恐怖や避難の流れを体験することで、災害への備えや適切な行動の重要性を深く理解できる内容となっています。VRやAR技術の活用は、防災訓練の効果を高める手段として、広まりつつあります。
浜松市による防災・減災対策の取り組み
浜松市は、「強くしなやかで、災害に強いまちづくり」を目指し、多角的な防災・減災対策に取り組んでいます。ここでは、具体的な取り組みとして、インフラ整備と防災体制の強化について詳しくご紹介します。
インフラ整備
浜松市では、南海トラフ巨大地震や集中豪雨に備えたインフラ整備を重点的に進めています。道路インフラでは、中山間地域にある国道152号などの斜面対策や、緊急輸送道路における橋りょうの耐震補強を行い、老朽化したインフラの改修も進行中です。
また、激しい雨による水害対策として、流域治水の取り組みを推進しています。地域全体で協力し、戦略的に浸水リスクを軽減する計画が実施されています。
加えて、上下水道の分野では基幹管路や下水処理施設の耐震化を進めるとともに、「浜松市総合雨水対策計画2024」に基づく雨水対策事業に取り組み、断水リスクを低減しています。
防災体制の強化
市域が広大な浜松市では、防災体制の強化が課題の一つです。その対策の一環として、防災倉庫を適所に設置し、非常食や資機材などの備蓄品を効果的に管理しています。土砂崩れなどで孤立しやすい地域への備蓄量を拡充する計画も進められています。
さらに、2024年度からは緊急速報メールや市公式LINEなどを活用した一括配信システムを導入し、避難情報を迅速に届けられるよう改善しました。また、消防指令管制システムを更新し、「映像通報システム」を取り入れるなど、災害時の情報伝達や救急対応を効率化しています。
減災の取り組みに関するまとめ
この記事では、日本における「防災」と「減災」の意義や取り組み、そして地方自治体による具体的な事例をご紹介しました。災害に備えるためには、自助や共助の意識を高める個人の努力と、地域や行政によるインフラ整備や防災体制の強化が重要です。
浜松市では、ハード面とソフト面の両方を充実させることで、より安全で災害に強い社会を築く取り組みを進めています。これらの取り組みを学びながら、日々の備えを進めていくことが、未来の災害に対応する最善の方法であると言えるでしょう。