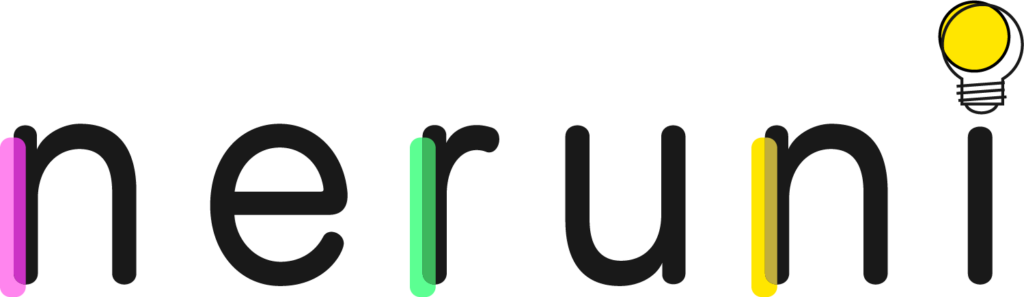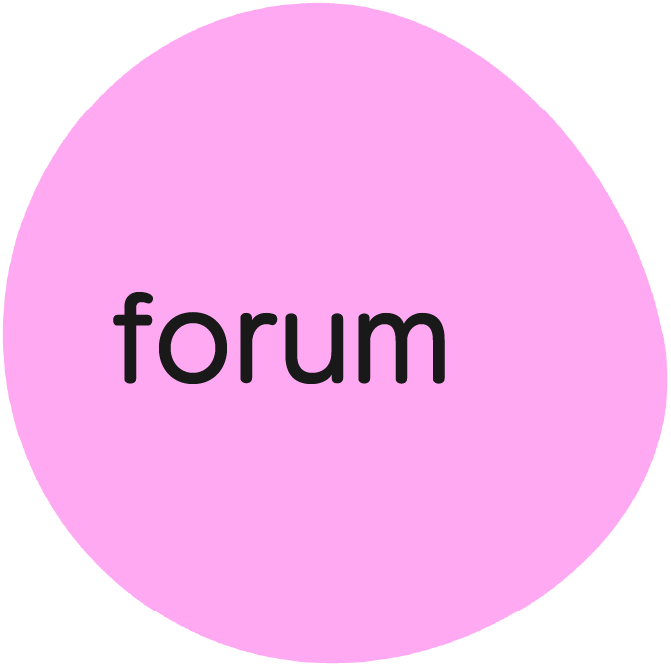害獣対策は、農作物を守り地域経済を支えるため、また生態系バランスの維持や健康リスクの低減において重要です。電気柵や防獣ネットによる物理的な防御など、多角的な対策が求められます。この記事では、害獣対策の重要性や具体的な方法について解説します。浜松市の取り組み事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
害獣対策とは?
害獣対策とは、主に農作物や家畜を野生動物による被害から、農業資産を守るための取り組みを指します。具体的には、野生のイノシシ・シカ・サル・カラスなどが農地に侵入し、作物を食べたり荒らしたりすることを防ぐための方法です。害獣による被害は、単に作物を失うだけでなく、収穫後の経済的損失や、耕作意欲の低下など、農業経営に深刻な影響を及ぼすことがあります。
また、害獣の被害は農村地域だけにとどまらず、森林の植生への影響や、生態系全体のバランスにまで波及する場合も少なくありません。そのため、対策は一つの方法だけでなく、地域の実情に応じた多角的なアプローチが求められています。物理的に侵入を防ぐためのフェンス設置や、生態系を考慮した管理方法、最新テクノロジーを活用した対策などがその一例です。
害獣対策では、地域社会や農業者が安心して暮らし、農作業に専念できる環境を整えることが目指されています。問題を理解し、適切に対処することが、持続可能な農業や地域の発展につながると言えるでしょう。
農林水産省が推奨する地域社会での取り組み
農林水産省は、地域社会が一丸となって実践するべき「獣害対策の5か条」を提唱しています。これは、農地や集落を害獣の影響から守るための具体的な方法を示したもので、以下の5つの取り組みが挙げられています。
・エサ場(収穫残渣など)の除去:収穫後に残った作物や不要となった果樹を処理し、害獣が食べ物を見つけにくくする
・隠れ場所(耕作放棄地など)の排除:耕作放棄地や藪を整備し、害獣が潜みやすい環境を減らす
・畑をネットや柵で囲う:畑や果樹園を囲むことで、物理的に害獣の侵入を防ぐ
・組織的な追い払いの実施:地域が協力して害獣を追い払い、人間の住環境を「安全な場所」と認識させない
・適切な捕獲と密度管理:科学的調査に基づいた計画的な捕獲を行い、害獣の密度を調整する
これらの対策は、地域住民や行政が連携して取り組むことで初めて効果を発揮します。一部の対策、特に捕獲や密度管理は、行政主導で計画的に進められるべきですが、多くの活動は地域主体での取り組みが不可欠です。例えば、畑の囲いや耕作放棄地の整備など、住民が実践できる内容も多く含まれています。
具体策を実施することで、害獣による農作物への被害を効果的に減少させるだけでなく、地域社会の安全と農業経営の安定にもつながるでしょう。
害獣対策を講じる重要性
害獣被害は農業、地域環境、そして人々の健康に深刻な影響を及ぼす問題です。そのため、適切な対策を講じることは、持続可能な地域づくりに欠かせません。以下では、農業生産・生態系バランス・健康リスクの観点から、害獣被害の重要性について解説します。
農業生産の保護
日本では、イノシシ・シカ・サルといった野生動物が農地に被害を与え、その結果、毎年深刻な損失が発生しています。農林水産省の調査によると、野生鳥獣による農作物被害額は年間約150億円にも上り、特にイノシシやシカが占める割合が高いのが現状です。こうした経済的打撃は、地域の農家にとって収入の大幅な減少を意味し、生活に深刻な影響を及ぼします。
さらに、被害が長期化することで、農業への意欲が低下し、離農を選択する農家が増加することも懸念されています。このような状況が進行すると、耕作放棄地が増え、結果として害獣の生息範囲が広がるという悪循環につながる可能性があります。
農業生産を保護するためには、被害を未然に防ぐ対策だけでなく、被害が発生した後の支援体制も重要です。害獣対策は単なる農業保護にとどまらず、地域経済全体に関わる取り組みであり、その重要性はますます高まっています。
生態系バランスの維持
害獣による影響は農作物の被害に留まらず、地域の生態系にも深刻な悪影響を及ぼしています。イノシシやシカなどの害獣が増加すると、これらが餌や生息空間を奪うことで在来種の生活圏を脅かし、地域固有の生物が減少してしまう可能性があるのです。また、遺伝的多様性の低下を招き、生態系全体の健康が損なわれる懸念もあります。
さらに、希少植物が害獣の食害によって失われるケースも報告されています。例えば、山林や草原に自生する希少な花や国の天然記念物が食い荒らされ、絶滅の危機に瀕することも珍しくありません。地域の生態系の豊かさが失われ、生物多様性の維持が難しくなることが予測されます。
健康リスクの低減
イノシシやハクビシンなどの動物は、感染症の媒介となるリスクがあり、住民や家畜に健康被害をもたらす可能性があります。野生動物が媒介する病原体が人間に感染し、健康危機を引き起こす事例も報告されています。また、これらの動物が農作物を荒らすことで農地が汚染され、食品衛生上の問題が発生する懸念もあります。
さらに、害獣対策が十分でない場合、被害を防ぐために農薬の使用量が増加する傾向があります。この結果、環境への悪循環が生まれ、土壌や水質汚染といった新たな問題が派生する可能性もあるでしょう。また、農薬使用の増加は生態系全体に影響を及ぼし、害虫や病原体の抵抗性を高めることで、さらなる対策の複雑化を招くことも懸念されます。
獣害が発生する主な要因

獣害は自然環境や人間社会の変化が複雑に絡み合う中で、発生・深刻化しています。ここでは、獣害が発生する6つの要因について解説します。
天敵の不在
日本では、かつて野生動物の個体数を調整していたオオカミやツキノワグマといった大型肉食獣が、長い歴史の中で減少あるいは絶滅してしまいました。その結果、現在はイノシシやシカなどの大型草食動物が天敵のいない環境で増加し、農地や里山での被害が拡大しています。これらの動物は適応能力が高く、繁殖力も強いため、個体数が増える一方で、その管理が難しくなっているのが現状です。
天敵はただ個体数を減らすだけでなく、野生動物の生息地や行動範囲を制限する重要な役割を持ちます。しかし、日本では天敵がいなくなったことで、野生動物が特定の区域にとどまる必要がなくなり、人間の生活圏に進出する機会が増えました。このような状況が農作物の被害を増加させ、結果として農家の経済的損失や生活環境への悪影響につながっています。
過疎化と高齢化
日本の農村部における過疎化と高齢化は、獣害問題を一層複雑化させる大きな要因です。農村地域では、人口の減少や高齢化に伴い、農地や里山を適切に管理する人手が不足しています。その結果、耕作放棄地が増加し、これが野生動物にとって絶好の隠れ場所や餌場を提供する形となっているのです。特に耕作放棄地は、草や雑木が茂りやすく、イノシシやシカといった害獣が生息するには理想的な環境を形成します。
さらに、かつては里山が地域住民によって適切に管理されていましたが、薪を取る習慣や山菜を採る文化が衰退した現在では、こうした管理が行き届いていません。里山が未管理のまま放置されると、山から野生動物が人里に降りてくるリスクが高まります。また、高齢化した農家では防護柵の設置や点検作業が負担となり、防護が不完全になるケースも見受けられます。
餌場の提供
獣害が発生する一因として、人間が与えてしまう餌場の存在が挙げられます。農地に放置された収穫残渣や不要作物は、野生動物にとって栄養源となり、害獣を引き寄せる要因となっているのです。これらの残渣は農家にとっては廃棄物に過ぎませんが、イノシシやシカにとっては貴重な食料となるため、放置すれば害獣が農地周辺に集まりやすくなります。
また、適切に管理されていない耕作放棄地や人工林も、害獣にとって魅力的な環境となり得ます。特に人工林では、樹木の実や若葉が豊富なエサとなり、野生動物が人里に近づくきっかけを作ってしまうことがあるのです。このような状況は、農作物の被害だけでなく、地域全体の生態系や住民の生活環境への悪影響にもつながります。
狩猟者の減少
近年では、狩猟者の減少が獣害増加の一因となっています。狩猟免許の取得者数は増加しているものの、実際に狩猟登録を行い活動に従事している人数は減少しており、その背景には高齢化や地域の人口減少が挙げられます。特に、従来の狩猟活動を担っていたベテラン猟師たちが引退を余儀なくされる一方で、若い世代の狩猟者が十分に育っていない現状が問題となっています。
狩猟者の減少は、害獣の個体数管理を難しくし、結果として被害が拡大している状況を招いています。農作物被害や生活圏への侵入リスクを高めるだけでなく、交通事故や生態系の乱れといった問題にも発展しかねません。狩猟活動が減少することで、害獣密度の管理能力が低下し、農村部では効果的な対策を講じるのが難しい現状があります。
また、野生動物を捕獲するための資金や技術支援が不足していることも、この問題を一層複雑化させています。狩猟者の数を回復させるためには、若者の参加を促進する取り組みや狩猟活動への理解を深める教育が必要です。
森林内の食料不足
環境の変化や森林伐採が進む中で、野生動物は本来の生息地で十分な食料を確保できなくなりつつあります。特に、森林資源の開発や土地利用の変化が進むことで、野生動物が利用できる自然の餌場が減少しています。この結果、食料を求めて人里に降りてくる頻度が増加し、食害や畑の荒らしなどの被害を増加させているのです。
また、地域の野生動物が栄養不足に陥ると、健康状態が悪化し、感染症の発生リスクが高まる可能性があります。このような事態は、人間や家畜への感染症リスクをもたらすため、地域社会全体で対応する必要があります。
気候変動
地球温暖化や気候の変化により、野生動物の活動範囲や繁殖パターンが変化しています。例えば、暖冬傾向や降雪量の減少がイノシシやシカの活動期間を延ばし、個体数が増加する原因となっているのです。また、幼獣の死亡率が低下することで繁殖効率が向上し、害獣の密度がさらに増加しています。
また、猛暑の影響や降雨パターンの変化により、害獣が本来の生息地を離れるケースも増えています。このような状況が、農作物の食害や生態系の乱れといった問題を引き起こしているのです。
気候変動による影響は、地域ごとに異なる対応が必要であることも課題です。例えば、高地では雪の減少により野生動物の移動が容易になる一方で、低地では降雨量の増加が農作物の成育環境に影響を与える場合があります。このような多様な影響を総合的に考慮し、適切な対策を講じることが大切です。
主な害獣対策の方法
獣害対策を講じる際には、被害を未然に防ぐためのさまざまな方法が用いられています。それぞれの対策には特徴があり、地域や被害状況に応じた工夫が必要です。以下に、主な5つの害獣対策について解説します。
電気柵の設置
電気柵は、害獣が触れた際に軽い電気ショックを与え、心理的な学習効果によって侵入を防ぐ方法です。この「心理柵」は、イノシシやシカなどが農地に接近するのを効果的に防ぎます。
ただし、効果を発揮させるためには、設置場所の選定やメンテナンスが重要です。例えば、草が生い茂ると通電が弱まるため、定期的な草刈りが欠かせません。また、害獣が「通れる場所」と誤認しないように、常に電気が通っている状態を保つ工夫も求められます。
防獣ネットやフェンスの利用
物理的に害獣の侵入を防ぐ方法としては、防獣ネットやフェンスの設置が一般的です。これらは、シカやイノシシなどの動物が農地に侵入するのを物理的に遮断する手段で、高さや強度を害獣の種類に応じて選ぶ必要があります。
設置後も効果を持続させるためには、ネットやフェンスに開いた穴の修繕や緩んだ部分の点検を定期的に行うことが重要です。また、作業の便を図るために、林縁部との間に管理用の通路を設けることが推奨されています。
動物撃退器の設置
センサーで害獣を検知し、音や光、水の噴射などで追い払う動物撃退器は、農地への害獣侵入を抑止するための近代的な装置です。この方法は、イノシシやシカ、さらには鳥類にも有効で、夜間でも自動的に作動することで農地を守ります。
ただし、害獣が装置の音や光に慣れてしまうと効果が薄れるため、音の種類や照射パターンを変えるなど、定期的な調整が必要です。また、装置の設置場所によっては近隣住民に迷惑をかける恐れもあるため、適切な運用が求められます。
忌避剤の使用
忌避剤は、害獣が嫌がる臭いを発して侵入を防ぐ方法です。この方法は、農作物を直接的に守るだけでなく、動物が近づくのを心理的に抑制する効果があります。
忌避剤の選定は、対象となる動物種に合わせて行う必要があります。また、風や雨などの影響で効果が薄れるため、定期的に再塗布することが大切です。コストや手間を考慮しつつ、他の対策と組み合わせることで効果的な害獣抑止が期待できます。
最新テクノロジーの活用
近年では、モニタリング技術やデータ分析を活用した害獣対策が注目されています。例えば、カメラやセンサーを使用して動物の出没時間や侵入経路を記録し、そのデータを分析することで、効果的な対策を立案することが可能です。
このような技術を導入することで、侵入防止策の設置場所や捕獲活動のタイミングを最適化できます。また、ICT技術を駆使することで、被害地域同士が情報を共有し、広域的な対策を展開する取り組みも行われています。
浜松市における害獣対策の取り組み例
浜松市では、野生鳥獣による農林産物被害の軽減と市民生活への被害回避を目的に、「浜松市鳥獣被害防止計画」を策定し、総合的な対策を推進しています。イノシシやニホンザル、ニホンジカを含む複数の鳥獣を対象に、さまざまな取り組みを行っています。
主な取り組み内容は、以下の通りです。
・防護柵の設置:農作物の被害を防ぐため、浜松市では防護柵や追払い資材、忌避効果資材の購入費を補助しています。
・捕獲活動の強化:GPS首輪を用いたニホンザルの生息状況調査や、シカ自動捕獲システムの導入など、先端技術を活用し効率的な捕獲活動を進めています。また、わな通知システムも導入し、害獣管理の精度を高めています。
・環境整備の推進:緩衝帯の設置、追上げや追払い活動、放任果樹の除去など、集落主体で環境を整備する取り組みが進められています。
・鳥獣被害対策実施隊の活動:2017年に設置し、防護柵の点検・生息環境の管理・住民対象の研修会実施など、地域社会と連携した多面的な活動を展開しています。
・教育・啓発活動:幼稚園での寸劇を通じた勉強会や、技術指導者育成研修など、市民や次世代への啓発活動も活発に行われています。
これらの取り組みにより、浜松市は地域全体で協力しながら、被害軽減と自然環境の調和を目指しています。他の自治体でも参考にできる実践例と言えるでしょう。