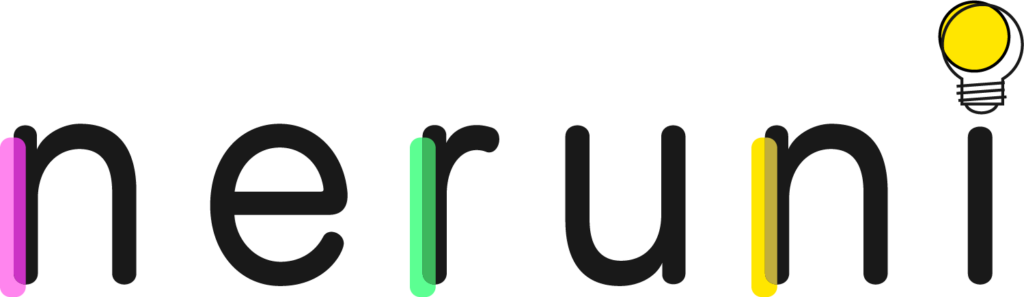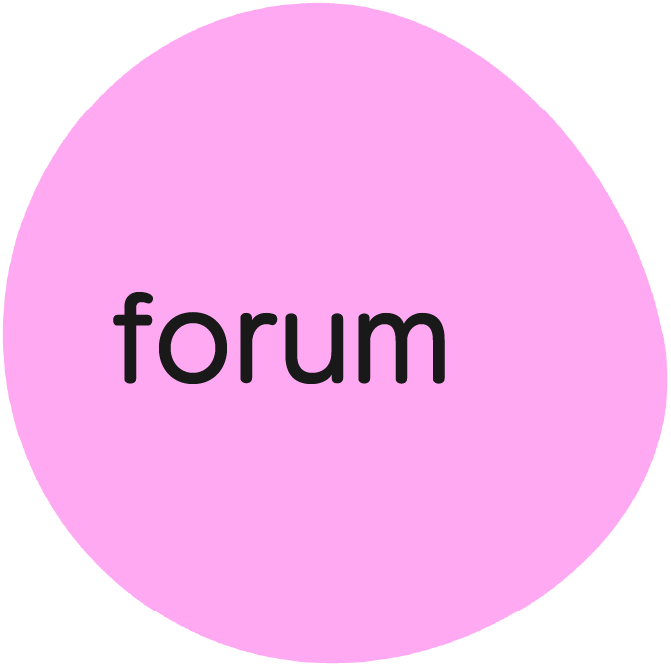近年、社会全体で取り組むべき重要な課題として、「子育て支援」が注目されています。多様な家庭が安心して子育てを行える環境を整えるため、自治体や企業が連携してさまざまな支援策を実施しているのです。
この記事では、子育て支援の具体例や、自治体と官民連携による取り組み事例を紹介します。
子育て支援とは?
「子育て支援」とは、家庭が安心して子どもを育てられる環境を整えるため、経済面・健康面でサポートする取り組みや制度を指します。例えば「児童手当」は、子育て世代の経済的負担を軽減するための代表的な施策です。0歳から中学生までの子どもを持つ家庭に対して定期的に金銭を支給し、生活の安定を図ります。
さらに、自治体が主導で行う健康診断や育児相談会、予防接種の無料化など、子どもの健康を守るためのサポートも充実しています。各自治体が連携して、転入時の予防接種履歴の引き継ぎなども無償で行われるため、親の負担が軽減されます。
また、2015年に施行された「子ども・子育て支援新制度」は、幼児教育や保育、地域の子育て支援の質・量を向上させるために設けられた制度です。核家族化や共働き家庭の増加に対応し、すべての家庭が利用できるよう設計されています。一時預かり・病児保育・ファミリーサポートなど、さまざまな子育て支援サービスが利用可能となり、保護者が安心して子育てに専念できる環境が整えられています。
子育て支援の具体例

子育て支援の取り組みとして、経済的な援助や保護者へのサポートが挙げられます。以下では4つの具体例を挙げ、それぞれ詳しく説明します。
児童手当
児童手当は、子どもを育てる家庭への経済的な支援を目的とした制度です。0〜2歳の子どもには月15,000円、3歳以上の子どもには月10,000円(第3子以降は15,000円)が支給されます。
2023年に改正され、家庭の経済的負担がより軽減されるよう、対象範囲が拡大され、支給回数も年3回から年6回に増えました。また、3人目以降の子どもには支援が強化され、多子世帯の負担も軽減されています。
児童手当は、少子高齢化が進む日本において家庭の経済的負担を軽減することを目的としており、子育てしやすい社会を実現するための基盤となる制度です。
乳幼児医療費助成
乳幼児医療費助成は、多くの自治体で就学前の子どもを対象に、一部または全額の医療費を支援する制度です。子どもの病気やケガをした際の医療費負担を軽減し、安心して適切な医療を受けてもらうことを目的としています。
助成対象となる年齢を「15歳未満」としている自治体も多く、東京都では2023年4月より、対象年齢を「中学生以下」から「高校生以下」に引き上げました。各自自体で設定している年齢や助成内容に違いはあるものの、子育て家庭の経済的負担を和らげる目的は同じです。
子育て支援センターでのサービス
子育て支援センターは、地域の乳幼児とその保護者が気軽に集まり交流を深める場です。育児相談や情報提供を行い、親同士が交流できる機会も設けています。
保健師による発達チェックや育児相談、親子の交流イベントなども実施され、地域全体で子どもの成長を支援しています。子育て中の不安や悩みを軽減するためのサポートが充実しており、保護者にとって心強い存在です。家庭が安心して子どもを育てるための拠点となっています。
訪問育児サポーター
訪問育児サポーターは、地域の子育て経験者が家庭訪問し、育児の不安や悩みを聞いてアドバイスをしたりする制度です。地域ごとに名称は異なり、「育児支援サポーター」「子育てサポーター」などと呼ばれることもあります。特に育児に孤立感を感じる保護者にとって、心強いサポートとなります。
各自治体では、サポーターの育成や配置を推進しており、子育てを終えた中高年世代には養成講座を実施し、今の子育ての困難さを理解してもらう配慮もされています。
官民連携における子育て支援の取り組み事例
子育て環境の改善を目指すため、自治体と企業も協力して取り組んでいます。ここでは、以下2つの官民連携プロジェクトを紹介します。
「官民連携事業研究所」と「ママスクエア」の業務提携
“「官民連携事業研究所」と「ママスクエア」は、女性の社会進出と子育て支援を強化するための取り組みとして、2023年11月に業務提携を締結しました。官民連携事業研究所は、自治体と企業を結びつける専門家であり、数多くの連携事業を手掛けてきました。一方、ママスクエアは、子連れ勤務が可能なワーキングスペースの運営など、子育て世代の柔軟な働き方を支援する企業です。
2社の提携により、南あわじ市での子育てコンソーシアム運営支援や、働くママのリスキリング支援を展開し、子育てと仕事の両立を支援しています。例えば、ママスクエアはIT関連講座を実施し、地元企業とのマッチングサポートを行っています。また、働くママのリアルな声を企業の制度に反映させるため、意見交換の場を設けるなど、具体的な施策を進めています。”
あかちゃんとそなえの輪推進プロジェクト
ピジョン株式会社が官民連携事業研究所と協力して進める「あかちゃんとそなえの輪推進プロジェクト」は、食品ロス削減や子育て支援、そして防災対策をテーマにしています。2021年に始まり、自治体との連携を拡大し続けています。
このプロジェクトでは、神奈川県鎌倉市や奈良県生駒市など、複数の自治体と連携し、ベビーフードの寄贈を行うことで食品ロス削減に貢献しました。また、赤ちゃん向け防災用品「ソナエッタ」を広め、防災の重要性を啓発しています。自治体広報誌にも防災情報を掲載し、新商品開発にも取り組んでいます。
こうした活動により、住民の声を直接聞き、地域のニーズに合わせた支援が可能となっています。「赤ちゃんの防災」を広めるための取り組みを通じて、赤ちゃんとその家族が安全に過ごせる社会の実現に向け、多くの自治体と連携していくことが期待されています。
【浜松市】自治体における子育て支援の取り組み事例
浜松市は子育て世代を応援し、結婚から教育までの切れ目ない支援に取り組んでいます。以下に主な取り組み事例を紹介します。
子育て支援施設とサービス
“子育て支援ひろば:
就園前の子どもと保護者が集える場所で、週4~7日開催。職員が常駐し、遊び場提供、育児相談、情報提供を行っています
ファミリー・サポート・センター:
子育ての援助を求める人と提供する人をマッチングする会員制システムです。
病児・病後児保育:
病気や回復期の子どもの一時預かりを行い、保護者の就労支援をしています。
教育支援
発達支援広場(たんぽぽ広場):
言葉の遅れや落ち着きのなさなど、発達に心配がある子どもの成長を促す支援の場です。単に子どもの成長を促すだけでなく、保護者に対しても子どもの特徴に合わせた関わり方をアドバイスし、前向きな子育てを支援しています。
アウトリーチ型学習支援:
浜松市では、交通の便が悪い地域や不登校の子どもたちのために、アウトリーチ型の学習支援も実施しています。
経済的支援
フードパントリー事業:
経済的に困窮している子育て家庭に対して、食料品や生活用品を無償で提供する事業を実施しています。令和6年度の第4期は終了しましたが、今後も継続される可能性があります。
医療費助成:
1.乳幼児医療費助成制度
対象:0歳から6歳以下の小学校就学前までの乳幼児
内容:医療機関での保険診療分の医療費が助成されます
2.小学生・中学生・高校生世代の医療費助成
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
内容:通院は1回500円の自己負担、入院は自己負担なし
子育て支援に関するまとめ
子育て支援は、子どもたちが健やかに成長し、笑顔で過ごせる社会を実現するための大切な取り組みです。自治体や官民連携が連携しながら、家庭が抱える不安や負担を軽減し、安心して子育てができる社会を目指しています。
各自治体が積極的に取り組むことで、地域全体で子育てをサポートする体制が整備されてきました。官民連携による取り組みも注目されており、企業と自治体が協力して子育て環境の改善を目指しています。今後もさまざまな支援策が拡充され、より多くの家庭が安心して子どもを育てられる社会が実現されることが期待されます