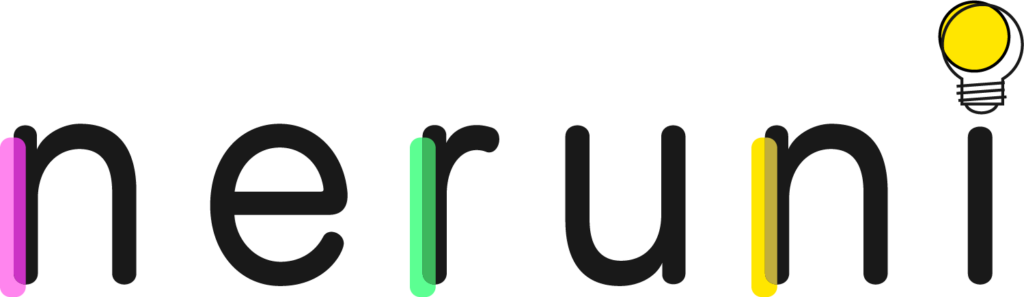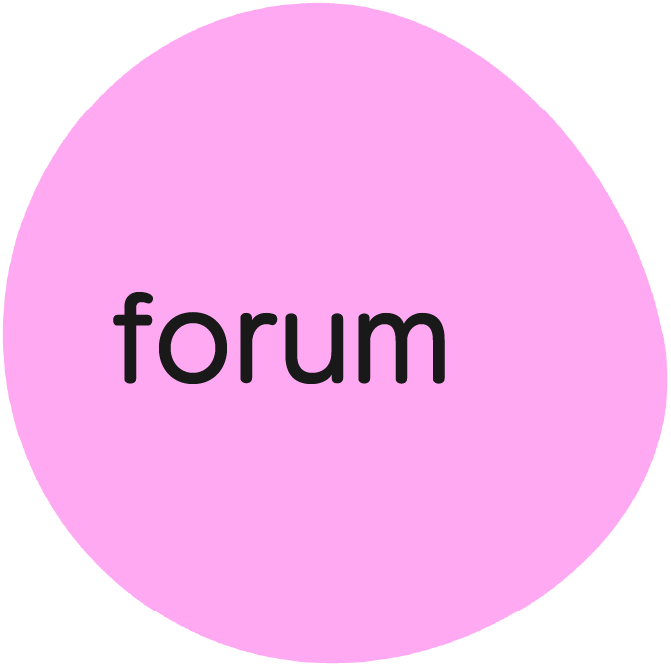ユニバーサルデザインは、誰もが使いやすく、快適に過ごせる環境を目指す設計理念です。私たちの日常生活には、多くのユニバーサルデザインが取り入れられており、さまざまな施設や製品、サービスで目にします。
この記事では、身の回りの具体例や、自治体における取り組みを紹介し、ユニバーサルデザインの重要性や実際の効果について解説していきます。
ユニバーサルデザインとは?
ユニバーサルデザインとは、「すべての人の使いやすさを考えられたデザイン」のことを指します。年齢・性別・国籍・身体能力などに関わらず、誰もが利用しやすいように工夫されたものです。特定の人に限定せず、すべての人が快適に利用できることを目指しており、建物や施設だけでなく、公共空間や製品、サービスなどさまざまな分野で取り入れられています。
例えば、従来のバリアフリーでは、車いす利用者のための専用リフトなどが設置されていましたが、ユニバーサルデザインでは、初めから誰でも使えるエレベーターを設けるといった工夫がなされます。車いす利用者はもちろん、高齢者や子ども、荷物を持っている人など、すべての人がより便利に利用できる環境を整えることが目的です。
ユニバーサルデザインは一度完成すれば終わりではなく、常に進化し続けるものです。あるデザインが特定の人には便利でも、他の人にはそうでない場合もあります。そのため、より多くの人が利用しやすくなるように、デザインは絶えず改良され続けています。
街中や公共施設、住宅、学校、さらにはメディアに至るまで、あらゆる場面で求められています。身の回りをユニバーサルデザインの視点で観察してみると、その重要性や広がりを実感できるでしょう。
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いは、対象とする人々の範囲にあります。バリアフリーは特定の障害を持つ人々や高齢者を対象に、利用の障壁を取り除くことを目的としているものです。
例えば、バリアフリーの例として「点字ブロック」が挙げられますが、視覚障害を持たない人にとっては直接的な必要性は低いものとなっています。これに対してユニバーサルデザインでは、視覚障害者に限らず、誰でも利用できる音声案内システムを導入することで、多くの人が利便性を感じられるように設計されています。
誰を対象としているのかに違いはあるものの、どちらも一人ひとりが快適に暮らせる世の中を目指している点では共通しています。
ユニバーサルデザインの7原則

ユニバーサルデザインには、あらゆる人の快適性を考える上で指針となる、7つの原則があります。提唱者のロナルド・メイス博士を中心に、建築家やデザイナー、技術者、研究者などの専門家グループによってまとめられました。ここでは、それぞれの原則について詳しくみていきましょう。
誰にでも公平に利用できること
ユニバーサルデザインでは、すべての人が同じ方法で製品やサービスを利用できることを目的としています。また、その上で特定の人が差別感や屈辱感を感じないデザインであることも重要です。
例えば、自動ドアや段差のない歩道、エレベーターなどは、車いす利用者・ベビーカーを利用する親・高齢者など、誰にとっても不便さを感じることなく利用できる設計です。このようなデザインは、特定の人々に特別扱いされていると感じさせることなく、自然に利用できるため、真に公平なデザインであると言えます。
使う上で自由度が高いこと
利用者の状況や好みによって自由に使えることも大切です。使う上での自由度が高いほど、さまざまな人が利用しやすくなります。
例えば、男性用トイレにもおむつ交換スペースを設けることで、赤ちゃん連れのお父さんにも便利です。また、右利き・左利きどちらでも使いやすいハサミは、すべての人がストレスなく利用できます。
多様な利用者のニーズに応じて柔軟に使い方を選べる環境が整っていることで、誰もがより快適に自由に利用できるようになります。
使い方が簡単ですぐわかること
使い方が直感的で、分かりやすいことが求められます。複雑な操作が不要で、誰でもすぐに使えるように配慮されたデザインが理想です。目立つ色や大きなボタン、レバー、スイッチなどを用いることで、一目で使い方が理解できるようになります。
例えば、扉を開けるためのボタンや電気を点けるためのスイッチは、視覚的に分かりやすく配置されるべきです。さらに、点字やイラストを使用することで、視覚に障がいのある方でも利用が容易になります。
操作をシンプルにし、特別な技術や力を必要としないデザインは、誰にとっても使いやすく、安心して利用できる環境を整えます。
必要な情報がすぐに理解できること
すべての人にとって必要な情報を伝えることも大切です。視覚・聴覚・触覚などの異なる方法を組み合わせることで、より多くの人が理解しやすくなります。
例えば、駅では多言語対応のアナウンスとディスプレイ表示を組み合わせており、外国からの訪問者にも分かりやすい情報提供を実現しています。また、複数の手段で情報を伝えることにより、アナウンスを聞き逃してもディスプレイで確認できるため、安心感が増します。
トイレの場合、イラストや大きな文字で表記することで、一目で男女や多目的トイレが識別できます。トイレ入口での機械による音声案内も、視覚に障がいのある方にとって便利です。このような工夫により、必要な情報がすぐに理解でき、多くの人が安心して利用できる環境が整えられます。
うっかりミスや危険につながらないデザインであること
利用・活用に失敗した場合でも安全な設計(フェイルセーフ)にしておくという観点も重要です。例えば、パソコンの「戻る」ボタンは、誤ってデータを消してしまった場合でも簡単に元に戻せるため、大切なデータを失わずに済みます。
また、駅のホームドアは利用者がホームに転落することを防ぐものですが、特に視覚や聴覚に障がいのある方にとっては、電車との接触事故を避ける役割を果たしています。洗濯機が動作中にフタを開けると自動で停止する機能も、うっかりミスや危険を防ぐための工夫の一例です。
安全に配慮した設計により、誰でも安心して利用できる環境が整えられます。
無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること
すべての人の使い勝手を考えると、自然な姿勢で、強い力を必要とせずに操作できることも大切です。例えば、自動販売機の中には、低い位置に商品ボタンが配置されているものや、かがむことなく商品を取り出せるよう取り出し口が工夫されているものがあります。
また、センサー式の蛇口は、手をかざすだけで水が出るため、ひねる動作が不要です。料理中で手が汚れている場合や、力の弱い方や手に問題がある方でも簡単に使用できます。身体への負担を減らし、少ない力で楽に使用できる工夫が必要です。
アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること
最後に、誰もが使いやすいスペースと大きさを確保することも重要です。例えば、車椅子対応のタクシーや広い通路の改札機、多目的トイレなどは、さまざまな身体状況の人が利用しやすい設計です。立位でも座位でも重要な要素が見えやすく、すべての操作部分に楽に手が届きます。
このような配慮が行き届いたデザインは、誰にとっても快適に利用できる環境を提供します。
身の回りで見かけるユニバーサルデザインの例

私たちの身の回りには、ユニバーサルデザインの考え方が取り入れられた製品やサービスがたくさんあります。それらの例をいくつか見てみましょう。
シャンプー容器の突起
多くのシャンプー容器にはポンプ上部にぎざぎざとした突起があります。この突起により、ユーザーは触るだけでリンスと区別できます。目が不自由な方や文字が読めない方だけでなく、シャワー中に目をつむっている状態でも、文字を読むことなく使い分けられるよう工夫されているのです。
照明スイッチ
家庭や職場で一般的に使われている照明スイッチにも、ユニバーサルデザインが取り入れられています。従来のスイッチと比べ、押す部分が大きくなったスイッチは操作しやすく、小さなスイッチでは困難だった方でも使いやすいものとなっています。
また、高齢者や手が不自由な方でも簡単に操作できるタッチ式や人感センサー式のスイッチも普及しており、両手がふさがっている場合でも点灯できるよう工夫されています。
段差のない敷居
段差は転倒の大きな原因であり、特に高齢者や障がいのある方にとっては僅か数ミリの段差でも大きな障壁となります。日常生活の中では、部屋間の敷居を低くし、車いすや高齢者も安全に移動できるようにすることが大切です。
例えば、玄関の階段をスロープにしたり、お風呂と脱衣所の段差を解消するリフォームなどがあります。
自動ドア
自動ドアは、重量センサーや人感センサーによって自動的に開閉する仕組みです。ドアを開ける力が不要なので、高齢者や小さな子ども、車いす利用者でも簡単に通行できます。また、両手に荷物を抱えたり、ベビーカーを押したりする人にとっても便利です。
多機能トイレ
多機能トイレは、車いす利用者や高齢者、子ども連れの方など、多様な人々が快適に利用できるよう設計されています。十分なスペースと設備が整っており、ベビーシートやオストメイト対応設備(病気やケガなどで排泄が困難な人が排泄処理や装具の交換ができるように配慮されたトイレ)が完備されています。
また、便座や手すりの位置も工夫されており、どの姿勢からでも操作しやすいように配慮されていることも特徴的です。
ピクトグラム(絵文字)
ピクトグラムは、誰にでも理解しやすいシンプルな絵で情報を伝えるデザインです。トイレや出口を示す記号など、言語に依存せずに一目で何を意味しているかが分かります。国外からの旅行者や文字を読み取りにくい高齢者、識字率の低い子どもでも直感的に理解できるため、あらゆる人にとって便利なデザインとして機能しています。
点字付き缶飲料
点字付き缶飲料は、視覚障がい者の方でも安心して飲み物を選べるように設計されています。特にアルコール飲料には、点字で「ビール」と記載されており、誤って飲むことを防いでくれます。ジュースと紛らわしいカクテルやチューハイなどの低アルコール飲料にも、点字やひらがなで「おさけ」と明示することで、識別しやすく工夫されているのです。
センサー式蛇口
センサー式蛇口は、手をかざすだけで水が出る仕組みが特徴で、握力が弱い高齢者や子ども、障がいのある方にも便利です。栓をひねる必要がなく、公共のトイレなどで多くの人に利用されています。触れずに水を出したり止めたりできるため、感染対策としても効果的です。
浜松市におけるユニバーサルデザインの取り組み例
浜松市は、ユニバーサルデザイン(UD)を市政の柱として積極的に取り組んでいます。以下に主な例を挙げます。
教育分野での取り組み
浜松市では、小中学生を対象としたUD教育を実施しており、2022年には小学4年生向けにバーチャル空間を活用したUD学習イベントを開催しました。
バーチャル空間上で実際のアクト通りのUD施設を忠実に再現した学習環境では、浜松未来総合専門学校の学生が空間設計を担当。oviceプラットフォームを活用し、動画やスライドを効果的に埋め込んだ形で児童の学びをサポートしました。
参照:ovice 浜松市の小学生が「ユニバーサルデザイン」を学ぶバーチャル空間 浜松未来総合専門学校学生が制作
条例制定と行政の取り組み
“2003年4月に全国に先駆けて「ユニバーサルデザイン条例」を施行。その基盤となる組織として、2000年度にはユニバーサルデザイン室を設置しました。
浜松市は「技術と文化の世界都市・浜松」というビジョンを掲げ、ユニバーサルデザインを市政の重要な柱として位置付けながら、市民・民間との協働を通じて思いやりのあるまちづくりを積極的に推進しています。
ユニバーサルデザインに関するまとめ
ユニバーサルデザインは、年齢、性別、国籍、身体能力などに関わらず、すべての人が快適に利用できる環境を目指す設計理念です。従来のバリアフリーが特定の障害者や高齢者向けの対応であったのに対し、ユニバーサルデザインは初めからすべての人の利用しやすさを考慮します。この考え方は、誰にでも公平な利用機会を提供し、使い方が簡単で理解しやすく、かつ安全性にも配慮することを重視しています。
私たちの身の回りには、自動ドアや多機能トイレ、ピクトグラムなど、様々なユニバーサルデザインが存在し、浜松市などの自治体でも積極的な取り組みが行われています。ユニバーサルデザインは一度完成すれば終わりというものではなく、より多くの人が利用しやすくなるよう、常に進化を続けながら、誰もが快適に暮らせる社会の実現を目指しています。