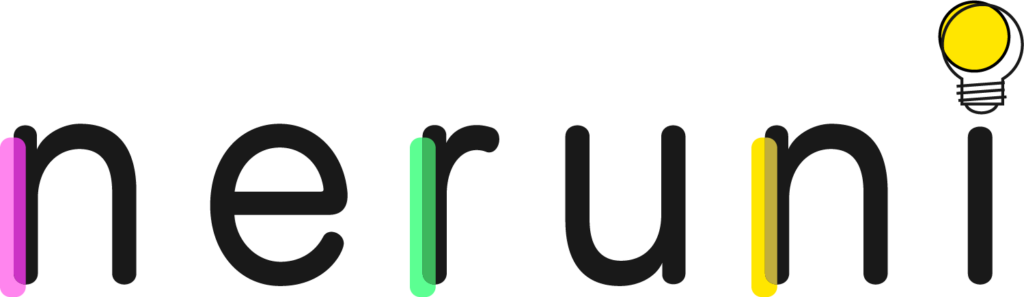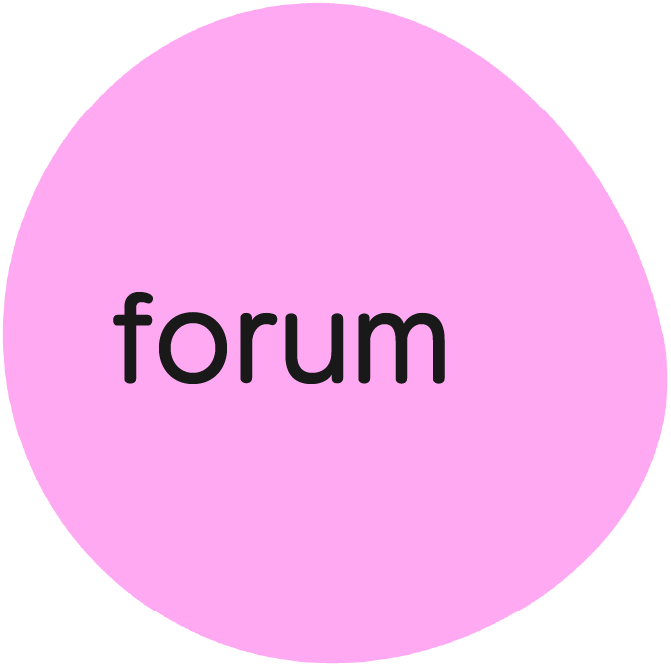超高齢化が進む現在、「高齢者見守り活動」の重要性はますます高まっています。しかし、地域社会のつながりが希薄化する中、従来のような日常的な近所付き合いによる見守りが難しくなっています。高齢者が安心して暮らせる環境を整えるためには、地域自治体や民間企業が協力し、見守りネットワークを構築することが重要です。本記事では、高齢者の見守り活動に関する現状とその重要性について深掘りします。具体的な事例や、需要が高まっているデジタルツールを活用した見守りサービスについて解説します。
高齢者の見守り活動に関する現状
昨今、日本の65歳以上の人口割合は約30%に迫っており、高齢者を支える環境は厳しい変化を遂げています。昭和50年には、三世代世帯が16.9%を占めていましたが、令和3年にはわずか4.9%に減少し、高齢者の単独世帯が増加しているのです。このような状況を踏まえ、特に一人暮らしの高齢者に対する見守り活動が重要視されています。
地方公共団体や社会福祉協議会では、継続的な見守り活動の必要性を感じ、地域包括支援センターや民生委員が主体となって高齢者の見守り活動を行っています。しかし、特定の主体だけでは限界があるのが現実です。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で従来の見守り活動に制約が生じ、新たな工夫が求められています。
高齢者の方々が安心して暮らせる環境を整えるためには、地域全体で支え合い、工夫を重ねることが重要です。各自治体の状況には差異があるものの、どの地方公共団体も見守り活動の重要性を強く認識しており、地域で必要な見守り活動の「量」と「質」を確保するために、さまざまな工夫を凝らした活動を続けています。今後も、一人ひとりの高齢者に寄り添った見守り活動が求められます。
参考:一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査結果報告書|総務省行政評価局
地域による高齢者の見守り活動の重要性
地域全体で支え合う見守り活動は、一人暮らしの高齢者の命を守るためにも重要です。以下では、地域による高齢者の見守り活動の重要性について解説します。

早期異変発見
一人暮らしの高齢者は、自宅で異変が起きた際に、発見が遅れるリスクが高まります。例えば、急な体調不良や事故が発生した場合、それに気付く機会が少ないため、迅速に対応するのは難しいです。しかし、近隣の方々や地域の見守り活動によって早い段階で異変を発見できれば、命を守ることにもつながります。
総務省の資料によると、令和5年の救急出動のうち、高齢者を搬送した割合は61.6%に達しており、多くの高齢者が突然の病気やケガに見舞われていることがわかります。その多くは家の中での転倒や入浴中の急病など、在宅中の一人でいるときに発生するものです。
また、高齢になると年齢とともに足腰が弱くなり、段差につまずきやすくなったり、お風呂やトイレで支えが必要になったりすることがあります。このような状況でも、見守り活動があれば、段差をなくしたり手すりをつけたりするアドバイスを受けることが可能です。しかし、一人暮らしをしていると、自身でその状況に気づかない場合もあります。危険な状況を放置すると大ケガにつながる恐れもあるため、第三者による見守りは重要です。
参考:「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表|総務省
安心感の提供
日常的に見守ってくれる人が近くにいることで、命を守るだけでなく、高齢者自身の安心感にもつながります。特に一人暮らしの高齢者にとって、万が一の時に頼れる存在がいることは心強いものです。
例えば、日常生活でのちょっとした不調やケガの際にも、近くで見守ってくれる人がいればすぐに助けを求められます。また、日常的に声をかけたり顔を見せたりすることで、近隣の人々とのつながりが強まり、高齢者は「誰かが自分を見守ってくれている」という安心感を持てます。
一人暮らしの高齢者にとって、見守り活動は生活の質を向上させる要素であり、地域全体で支え合うことで、より安心して暮らせる社会が実現します。高齢者の孤立を防ぎ、心の健康を保つためにも欠かせないものと言えるでしょう。
孤立防止
現代社会では人とのつながりが希薄になりがちですが、特に一人暮らしの高齢者にとって、この問題は深刻です。孤立することで、緊急時に助けを求めることが難しくなり、日常生活でも不安や孤独感が増してしまいます。近年の調査では、他者との交流が週1回未満の高齢者は要介護リスクが約30%上がり、月1回未満の場合は死亡リスクが約30%増加することが分かりました。
地域の見守り活動は、このような高齢者の孤立を防ぐために重要な役割を果たします。例えば、民生委員やボランティアが定期的に訪問し、声をかけることで高齢者の状況を把握し、必要な支援を提供できます。孤立を防ぐことで、高齢者の心身の健康を守り、より豊かな生活を実現できるのです。
家族の負担軽減
家族の負担軽減
見守り活動は高齢者自身だけでなく、家族にとっても精神的な負担を軽減する効果があります。老親が一人暮らしをしている場合、家族は遠く離れていても常に心配を抱えているものです。
見守り活動によって、老親の状況を定期的に確認できるため、家族の不安を軽減することにつながります。特に遠距離介護を行っている家族にとって、緊急時に素早い対応が取れる体制が整っていることは大きな安心となるでしょう。
また、見守り活動は「介護離職」のリスクを低減させる効果も期待できます。介護離職とは、家族や親族の介護をするために退職することを指し、特に働き盛りの世代にとって大きな問題となっています。厚生労働省の調査によると、2021年には約9万3,000人が介護離職を余儀なくされており、特に45歳〜49歳の世代においてその割合が高くなっています。
こうした状況の中、見守り活動によって老親の状態を把握しやすくなり、家族が無理なく介護を続けられるため、介護離職のリスクを低減することが期待されています。これにより、働き盛りの世代が職場を離れることなく老親を支えられ、企業にとっても人材の流出を防ぐ効果があると言えるでしょう。
地域社会の強化
地域による見守り活動は、単に高齢者を支援するだけでなく、地域全体のつながりを強化する効果があります。見守り活動を通じて、地域住民同士が互いに支え合うことで、地域社会全体がより強固なものになっていくのです。例えば、近隣の人々が定期的に顔を合わせたり、声をかけ合ったりすることで、地域全体の絆が深まります。
このような見守り活動は、高齢者だけでなく、地域住民全体にとっても安心感をもたらします。特に、災害時や緊急時には地域住民同士が連携し、助け合えるため、地域全体の安全性が向上します。さらに、見守り活動を通じて地域住民同士がコミュニケーションを深めることで、地域全体で孤立や孤独感が軽減される効果も期待されます。
浜松市における高齢者見守りの取り組み事例
静岡県浜松市では、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指し、さまざまな見守りサービスを展開しています。ここでは、さりげなくゆるやかに見守る「はままつあんしんネットワーク」についてご紹介します。
はままつあんしんネットワーク
浜松市の65歳以上の高齢者人口は年々増加しており、現在では約3.5人に1人が高齢者です。また、ひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯の割合も増加しています。このような状況を受けて、市民・地域・民間事業者・行政機関が連携し、「はままつあんしんネットワーク」を構築しました。
このネットワークの目的は、高齢者が日常生活で抱える不安を軽減し、安心して暮らせる環境を整えることです。地域の住民や事業者が協力して、高齢者の日常生活をさりげなく見守り、異変があった際には素早く対応できる体制を整えています。
例えば、新聞配達員やゴミ収集業者が日常業務の中で高齢者の様子を確認し、異常を感じた場合には関係機関に通報する仕組みがあります。市民の支え合いの心を基盤とした取り組みであり、多くの人々の協力によって成り立っているのです。
認知症の高齢者やその家族への支援だけでなく、虐待や消費者被害の防止といった課題への取り組みも、このネットワークの一環です。地域に暮らすすべての住民が安心していきいきと暮らせるまちづくりが進められています。
高齢者見守りにおけるデジタルツール活用の需要の高まり
高齢化が進む現代社会において、高齢者の見守り活動の重要性が増すと同時に、デジタルツールの活用の需要も高まっています。デジタル技術を活用することで、高齢者が安心して暮らせる環境を整え、地域全体の見守り活動をより効率的かつ効果的に行うことが可能です。
デジタル技術を駆使した高齢者見守りサービスには、AIを活用した介護プランの自動作成や、高齢者向けのオンラインサービスなどがあります。例えば、見守りセンサーを設置することで、日常生活の異変をリアルタイムで察知し、即座に対応することも可能です。これにより、高齢者の安全が確保されると同時に、家族の不安も軽減されます。
さらに、オンラインプラットフォームを利用することで、高齢者が地域コミュニティに参加しやすくなる点も注目されています。地域住民同士のコミュニケーションが促進され、孤立感や孤立死のリスクを軽減するだけでなく、生きがいや楽しみを持つきっかけを提供することも可能です。地域イベントのオンライン化やデジタル掲示板を活用し、自宅からの移動が難しい高齢者でも、地域活動に参加しやすくなります。
また、デジタル技術を活用した見守りサービスは、高齢者の生活の質を向上させるだけでなく、自治体の業務効率化やコスト削減にもつながります。例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入することで、事務作業の効率化が図られ、職員の負担が軽減されます。これにより、限られたリソースを有効活用し、より多くの高齢者を支えることにつながるのです。
まとめ
超高齢化が進む現代社会において、高齢者見守り活動の重要性はますます高まっています。地域全体で支え合う見守り活動は、一人暮らしの高齢者にとって命を守るために欠かせないものであり、多くの面で高齢者の生活の質を向上させます。
例えば、近隣住民や民生委員、ボランティアが協力して高齢者の状況を把握し、異変があった場合に迅速に対応することで、安心して生活を送ることが可能です。また、介護離職のリスクを低減させる効果も期待されており、働き盛りの世代が職場を離れることなく介護を続けられる環境を整えることが期待できます。地域自治体や民間企業、地域住民が協力し、見守り活動を充実させることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現につながるでしょう。